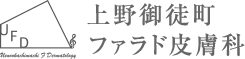2025.01.17 陥入爪
もう痛みに悩まない!陥入爪の原因と治療法を徹底解説

今回は、陥入爪(かんにゅうそう)について詳しく解説いたします。
陥入爪は、爪の端が皮膚に食い込み、痛みや炎症を引き起こす状態です。
適切な知識とケアで、痛みから解放されましょう。
1. 陥入爪とは?基本を理解しよう
陥入爪(かんにゅうそう)は、爪の端が皮膚に食い込み、炎症や痛みを引き起こす状態を指します。
特に足の親指に多く発生しますが、他の指にも見られることがあります。
この状態が進行すると、爪の周囲が赤く腫れ、化膿する場合もあり、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。
陥入爪の初期症状は軽度の違和感や圧痛から始まることが多いですが、放置すると歩行時の強い痛みや、感染による膿の排出といった深刻な症状に進行する可能性があります。
炎症が長引くと、爪の形状が変わり、さらに症状が悪化することもあるため、早期の対応が重要です。

この症状は、深爪や爪の端を丸く切りすぎること、不適切な靴の選択、足の変形具合、爪が足の指に対して大きいオーバーネイル、さらには遺伝的要因など、さまざまな理由で引き起こされます。
また、スポーツや立ち仕事、体重が重い方などで足に負担がかかる人や、糖尿病などで血行不良のある人も陥入爪になりやすい傾向があります。
陥入爪は誰にでも起こりうる一般的な疾患ですが、適切な知識を持つことで予防が可能です。
また、早期発見と適切なケアを行うことで、症状を軽減し、悪化を防ぐことができます。
なお、陥入爪と似た症状に巻き爪がありますが、両者は異なる状態です。
以下の表でその違いをまとめてみました。
| 項目 | 巻き爪 | 陥入爪 |
|---|---|---|
| 原因 | 爪が内側に巻き込む形状変化 | 爪の端が皮膚に食い込むこと |
| 炎症 | 必ずしも起きるわけではない | 炎症や化膿を伴うことが多い |
| 形状 | 爪が内側にカーブする | 爪の形状は通常通りでも発生 |
| 治療法 | 矯正具や手術で形を改善する | 食い込んだ部分の処置や手術 |
これらの違いを理解することで、自分の症状がどちらに該当するのか判断しやすくなります。
また、巻き爪で爪が皮膚に食い込んで陥入爪になってしまうこともあります。
本記事では、陥入爪に焦点を当てて解説していきますので、引き続きお読みください。
2.どうして陥入爪になるの?原因を徹底解説
陥入爪の原因は多岐にわたり、日常生活の中での習慣や環境が大きく影響します。
以下に、代表的な6つの原因を詳しく解説します。
1.深爪

爪を短く切りすぎると、爪の端が皮膚に覆われる形になり、爪が正常に伸びるスペースがなくなります。
この状態が続くと、爪が皮膚に食い込み、陥入爪を引き起こします。
また、深爪を繰り返すことで皮膚の炎症が慢性化し、爪の成長がさらに不均一になることがあります。
2.爪の切り方が不適切

爪の端を丸く切りすぎると、地面から爪への押す力が爪中心部は強いままですが、爪の両端は力が弱くなってしまうために力学的に爪が丸まってしまい、結果として爪が皮膚に食い込みやすくなります。
特に、爪切りの際に角を深く切り落とすことは避けるべきです。正しい爪の切り方を学ぶことが予防の第一歩です。
3.不適切な靴の選択

サイズが合わない靴や、先が細い靴は爪や指に過度な圧力をかける原因となります。
特に長時間歩行する場合や、立ち仕事が多い人にとって、このような靴は陥入爪のリスクを大幅に高めます。
柔らかく、足にフィットする靴を選ぶことが重要です。
4.遺伝的要因

家族に陥入爪の症状を持つ人がいる場合、同じような足や爪の形状を持つことが多く、陥入爪になるリスクが高まります。
遺伝によるリスクを完全に排除することは難しいですが、日常的なケアで予防が可能です。
5.外傷や圧力

足の指をぶつけたり、重い物を落とすなどの外傷が爪の成長に影響を与え、陥入爪を引き起こすことがあります。爪が欠けてしまい、その後に陥入爪になってしまう方も多くいらっしゃいます。
また、足の指に過剰な圧力がかかるスポーツや作業もリスク要因となります。
6.感染症や皮膚の状態

爪や周囲の皮膚に感染症が発生すると、皮膚が腫れて爪に食い込む形になりやすくなります。
湿気の多い環境で足が蒸れると、細菌や水虫などの真菌感染リスクが高まります。
陥入爪はこれらの原因が複雑に絡み合って発生しますが、日常生活の中で注意を払うことで予防が可能です。
自分の習慣や環境を見直し、リスクを減らすことが大切です。
3.こんな症状があれば注意!陥入爪の見分け方
陥入爪は、初期段階では軽い違和感から始まることが多いですが、症状が進行すると次のような具体的なサインが現れることがあります。
これらのサインを見逃さないことが、早期対処の鍵となります。
1.爪の側面の痛み
陥入爪の初期症状として最も多いのが、爪の側面に感じる痛みです。
この痛みは歩行や靴を履いたときに悪化することがあり、放置すると日常生活に支障をきたす場合があります。
2.赤みと腫れ
爪が皮膚に食い込むことで、その周辺が赤く腫れることがあります。
初期段階では軽い腫れにとどまりますが、進行すると炎症が広がり、腫れが顕著になることがあります。
3.肉芽組織の形成
症状が進行すると、爪の食い込んだ部分に肉芽組織と呼ばれる赤く盛り上がった柔らかい組織が形成されます。
この肉芽組織は触れると痛みを感じることが多く、感染のリスクも高まります。
また、この肉芽組織の盛り上がりによって、爪がより食い込むことになり症状が悪化するという悪循環になります。
4.化膿や膿の排出
爪の食い込み部分が感染すると、化膿して膿が出てくることがあります。
この段階になると痛みが強まり、歩行や靴の着用が困難になる場合もあります。
5.皮膚の変色
長期間放置された場合、爪の周囲の皮膚が変色することがあります。
これは炎症が慢性化しているサインであり、早急な治療が必要です。
陥入爪の症状は放置すると悪化し、治療が難しくなる場合があります。
これらの症状が見られた場合は、早めに専門医を受診することをお勧めします。
また、初期段階で適切なケアを行うことで、症状の進行を防ぐことが可能です。
4.専門医が教える陥入爪の治療法
当院では、症状の程度に応じて以下の治療法を行っています。
・棘状になった爪の端を切る取る
食い込んでしまった爪が、棘状に鋭くなっていることがあります。この場合、棘になった爪をきれいに切り取ることが大切です。ただ切り取るだけでなく、その後爪がスムーズに生えていけるように工夫して爪を切ります。
・ステロイドの塗り薬、液体窒素、抗菌薬の飲み薬
この3つは爪が皮膚に食い込んで起こった炎症や肉芽を軽減するための治療です。
陥入爪は、爪の食い込みを解除し、肉芽や赤く腫れた場所にステロイドや抗菌薬の塗り薬を塗る治療が基本です。
時に肉芽を小さくするために液体窒素治療を行うこともあります。菌が悪さをしている場合は抗菌薬の飲み薬の治療を同時に行います。
また、以下の3つは 爪が皮膚に食い込んでいる状態を解除する治療です。
・テーピング法
軽傷の陥入爪であればテーピングで改善が期待できます。
粘着力の強いテープを使って、爪が刺さっている部分の皮膚を爪から遠ざけるように引っ張ります。爪と横の皮膚に隙間を作り刺激を減らすイメージです。
ご自宅で継続的に行っていただきます。
食い込みの程度が軽く、腫れて少し痛みがあるという程度の症状はまずテーピングを行います。
1、2週間程で腫れと赤みが引いて改善するか様子を見ます。テーピング治療をしても腫れや赤み、痛みが改善しない場合は陥入爪手術を行うか検討します。
・ガター法
食い込んでいる爪と皮膚の間に柔らかいチューブを挟み、爪が皮膚に食い込まないようにします。 挟んだチューブは爪が伸びて外れるまでそのままにします。
・陥入爪手術
足の親指に行うことが多くなります。テーピングやぬり薬、飲み薬、液体窒素治療で改善しない場合に手術を検討します。
テーピングで数年にわたって治療して改善の無かった方が陥入爪手術後にすぐに良くなりとても楽になることも多く、テーピングなどの他の治療で痛みや腫れに改善がみられない場合は陥入爪手術を行うことをおすすめします。
・陥入爪手術のメリット
食い込みを物理的に取り除けるため、速やかに腫れ・痛みの改善が得られることです。また肉芽も切り取ることができます。
・陥入爪手術のデメリット
爪の幅が狭くなってしまうことと爪と側爪郭(爪の横側の皮膚)が離れてしまうため将来的な爪の変形のリスクがあります。できるだけ変形が起こらないように調節し手術致します。
陥入爪手術について、詳しくはこちらもご参照ください。
5.今日からできる!陥入爪の予防とケア方法
陥入爪を予防するためのポイントはいくつかあります。
どれも簡単なものばかりですので、ぜひ実践してみてくださいね。
- 正しい爪の切り方:爪は四角く、角を丸めすぎないように切り、少し長めに保ちましょう。
- 適切な靴の選択:足に合ったサイズで、先が広く、圧迫しない靴を選びましょう。
- 足の衛生管理:足を清潔に保ち、乾燥させることで感染を防ぎます。
- 定期的なチェック:足の爪や皮膚の状態を定期的に確認し、異常があれば早めに対処しましょう。
早めの対応が鍵!陥入爪の症状に気づいたら
陥入爪は、初期段階の症状を見逃さず、早めに対処することで悪化を防ぐことができます。
特に痛みや赤み、腫れなどのサインが見られた場合は、自宅で無理にケアしようとせず、専門医に相談することが大切です。
早期の対応は、治療期間を短縮し、再発のリスクも軽減します。
また、陥入爪の予防には、正しい爪の切り方や足に合った靴の選択が欠かせません。
日常的なケアを怠らず、自分の足や爪の状態に注意を払うことで、健康な足を保つことができます。
少しでも異常を感じたら、放置せず専門医の診察を受けましょう。
早めの行動が、快適な生活を取り戻す一歩になります。
もし「これは陥入爪かな?」と思ったら、お気軽に上野御徒町ファラド皮膚科までご相談くださいね。
この記事を書いた人

上野御徒町ファラド皮膚科 院長
上條 広章(かみじょう ひろあき)
- 資格
- 医学博士(東京大学大学院医学系研究科)
- 日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医
- 日本美容外科学会(JSAS)認定 美容外科専門医
- 日本レーザー医学会専門医
- 所属学会
- 日本皮膚科学会
- 日本美容外科学会(JSAS)
- 日本美容皮膚科学会
- 日本レーザー医学会
- 受賞歴
- 第7回日本皮膚悪性腫瘍学会賞(石原・池田賞)
- 第20回マルホ研究賞
- Poster Prize, 47th Annual Meeting of European Society for Dermatological Research
略歴
| 2012年 | 東京大学医学部医学科 卒業 |
|---|---|
| 2014年 | 藤枝市立総合病院 初期研修 修了 |
| 2014年 | 東京警察病院 皮膚科 |
| 2016年 | 東京大学医学部附属病院 皮膚科 |
| 2019年 | 東京大学医学部附属病院 皮膚科 助教 アトピー性皮膚炎専門外来、皮膚悪性腫瘍専門外来、レーザー専門外来担当 |
| 2021年 | 都内大手美容外科 入職 |
| 2022年 | 都内大手美容外科 本院 部長 美容皮膚科治療監修を担当 |
| 2022年 | 上野御徒町ファラド皮膚科 開院 |